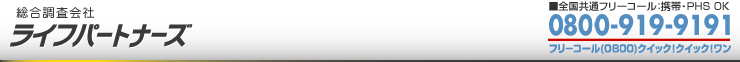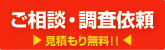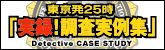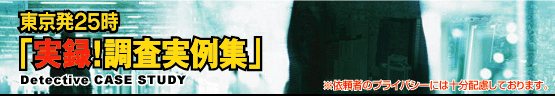
離婚の豆知識
離婚に関する知識を持っているのといないのでは、離婚する際や離婚後の生活などに大きな影響を及ぼす場合が多々あります。ですから、たとえ現在離婚を考えているわけではなくても、万一に備え最低でも簡単な離婚に関する知識を養っておく必要があるかと思います。実際に浮気調査をご依頼される方でも、離婚の決意は固いものの、どう離婚を進めていけばよいのかわからない方が以外にも大勢いらっしゃいます。従いまして、ここでいくつか離婚に関する情報をご紹介することにします。
《離婚の種類》
夫婦間で離婚の合意がなされない場合でも、いきなり裁判にて争うわけではありません。離婚は「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4パターンに分かれます。その詳細は以下のとおりです。
「協議離婚」
夫婦間の話し合いによって成立する離婚をいい、離婚のおよそ9割がこれに該当します。双方が離婚に合意し、離婚届を市町村役所へ提出すれば成立しますから、離婚の手続き費用は一切発生しません。ただし協議離婚で注意しなければならない点は、離婚に関する取り決め事項を「離婚協議書」に記載して、それを法的効力のある書類「公正証書」にしておく必要があるということです。これを怠ると、慰謝料・養育費・財産分与などの取り決め事項が離婚後守られなくなった場合、法的手段に移すことができず結局泣き寝入りとなってしまう可能性があるからです。
■離婚協議書
後々のトラブル防止として、双方で合意した離婚に関する取り決め事項を書面にし、両者が1通ずつ所持します。万一取り決めが守られなかった際には、離婚協議書を証拠に訴訟を起こすことは可能ですが、離婚協議書には法的効力がありません。したがって、これをもとに法的効力のある公正証書を作成する必要があります。離婚協議書の必要性は証拠という点、公正証書の作成をスムーズに行うといった点にあるといえるでしょう。
■公正証書
強制執行力があるため、慰謝料・養育費・財産分与などが約束通り支払われない場合、裁判を起こさなくても財産や給料を差し押さえる法的措置がとれます。金銭関係以外に執行力はありませんが、親権・面接交渉権などの決定事項も証拠として記載しておくとよいでしょう。公正証書は公証役場で作成してもらえます。
「調停離婚」
夫婦間の話し合いによる協議離婚が成立しない場合、家庭裁判所に調停の申し立てを行い、調停委員を交えて話し合った結果成立する離婚をいいます。離婚のおよそ9%がこれに該当します。協議離婚が合意に至らないからとすぐに裁判へ移るのではなく、「調停前置主義」といって通常は裁判の前に調停を行わなければなりません。また、調停は離婚を前提とするためだけのものではなく、夫婦関係の修復を目的とする「円満調停」といった意味合いも併せ持っています。
調停の申し立ては家庭裁判所にて行い、費用は2千円弱程度です。調停はおおよそ月1回の割合で繰り返され、たいてい半年以内に何らかの結論が出ます。調停でも合意に至らなかったり、相手が出頭しなかったりした場合は調停不成立となります。
「審判離婚」
調停が成立しそうもない場合でも、家庭裁判所が双方のために離婚する方がよいと判断した際には、調停委員の意見を考慮しつつ職権で離婚の処分を下すことができます。しかしながら、審判が下されてもどちらかがそれを不服として異議申し立てを行えば、その審判は効力を失い裁判へと移行します。審判離婚によって離婚するケースは年間100件程度と極めて少ないのが現状です。
「裁判離婚」
調停や審判においても離婚が成立しない場合、家庭裁判所から地方裁判所に場所を移し、裁判によって判決が下される離婚をいいます。裁判離婚では、通常弁護士に依頼して地方裁判所に離婚の訴えを起こすわけですが、裁判で離婚が認められるためには、民法で定められた離婚原因に該当していなければなりません。また、離婚原因を作った配偶者を有責配偶者といい、基本的に有責配偶者からの訴えはできないことになっています。
《離婚原因》
裁判で離婚を争う場合には、下記の離婚原因のどれかに該当していなければなりません。
「不貞行為」
不貞行為とは配偶者以外の異性と性的関係を持つこと、つまり浮気することをいいます。通常不貞行為として認められるためには、ホテルや浮気相手宅への出入りを証拠として提出する必要があり、いかに継続性のある交際かを立証することが裁判で優位に立てるかのポイントとなります。
「悪意の遺棄」
夫婦には「同居義務」「協力義務」「扶助義務」があるにもかかわらず、これらを故意に怠った場合のことをいいます。例としては、愛人を作って家に帰ってこない、生活費を渡さない、健康なのに仕事に就かないなどが挙げられます。
「3年以上の生死不明」
生きているか死んでいるかわからない状態が3年以上続いた場合に離婚原因として成立しますが、所在が不明であっても恐らく生きていると推測されるような場合には該当しません。前述の通り「調停前置主義」が原則ですから、裁判の前に調停を行うことになっていますが、この場合は相手がいないため調停は行わずに裁判となります。
「回復見込みのない強度の精神病」
夫婦は互いに協力して扶助しなければならない義務がありますが、夫婦としての精神的なつながりがなく、正常な夫婦生活を送る期待が見込めない場合には、医師の診断書をもとに裁判官が判断します。ただし、相手が病気になったからといって必ずしも離婚が認められるわけではなく、長期間病気を患った相手に対し誠心誠意看護をしてきたか、離婚後の看護の目途は立っているのかが重要になります。
「婚姻を継続し難い重大な事由」
夫婦生活がすでに破綻して修復が不可能な状態であればこれに該当します。例としましては性格の不一致、性生活の不一致、暴力・暴言・虐待、配偶者の親族との不和、ギャンブルなど過度の浪費、過度の宗教活動、刑務所に服役、その他様々な事由が挙げられます。
古い例で恐縮ですが、平成16年司法統計年報によりますと、離婚申立人が妻の場合に申し立て理由で多いのが性格の不一致・異性関係・暴力・生活費を渡さないなどで、夫の場合に多いのが性格の不一致・異性関係・家族親族と折り合いが悪いなどです。やはり異性関係は双方に当てはまるようです。
《不貞行為とその証拠》
■不貞行為とは
不貞行為は「配偶者以外の異性との性行為」と定義されます。離婚裁判では離婚原因として不貞行為を厳しく制限し、配偶者と愛人の性行為の存在を確認できる場合に限り不貞行為による離婚請求を認めています。従って、原告側は「性行為の存在を確認ないし推認できる証拠」を提示して、被告の不貞を立証しなければなりません。
■離婚訴訟を提出する場合
提訴理由を「不貞行為」にのみ限定してしまうと、不貞行為の証明が不十分な場合請求棄却で離婚が認められない場合が生じてしまいます。そこで「婚姻を継続し難い重大な事由」も併せて列挙し、最悪でも「離婚判決」は勝ち取るようにするとよいでしょう。
■不貞の立証と慰謝料請求
「不貞行為」が認められて離婚する場合と、不貞の立証が不十分で「婚姻を継続し難い重大な事由」が適応されて離婚する場合とでは、「離婚請求」に併せて提訴する「慰謝料請求」の結果に大きく影響します。「婚姻を継続し難い重大な事由」のみになってしまうと、内容次第では慰謝料が取れないか大幅に減額する場合が多いでしょう。ですから、配偶者が浮気をしている場合には、いかに証拠を押さえられるかが非常に重要となってきます。
■不貞を原因とした離婚・慰謝料請求をする場合
1.不貞が婚姻関係の破綻の原因であるという因果関係の立証が必要
例えば別居後や離婚後に不貞の証拠を確保した場合は、「不貞は婚姻破綻後の行為であり、婚姻破綻の原因とは認められない」と認定され慰謝料請求は認められません。
2.証拠類は合法的に確保されたものであることが必要
違法な盗聴行為による録音テープなどは裁判所への提出ができません。また、裁判では通常テープなどの再生は行われないため、ビデオテープの証拠は写真に、録音テープの証拠は文書化して提出する必要があります。
3.有責配偶者(浮気をしている当人)から離婚を迫られている場合
このような場合には調停・裁判に「相手方の不貞の証拠」を提示して、相手方の請求の棄却を求めることができます。
■不貞の証拠とは
1.不貞の証拠にならない例
・異性に愛の告白をする。
・ラブレターを書く。
・手をつなぐ。
・キスをする。
※不貞行為の定義は肉体関係を指しますので、上記のような行為だけでは不貞行為と見なされません。
2.不貞の証拠になる例
・ホテルに出入りする写真や映像。
・浮気相手の自宅に出入りする写真や映像。
・車内や公園などでの性交渉と判断できる写真や映像。
※例えば急に具合が悪くなりホテルに立ち寄ったなどと反論され、不貞の立証が不十分と見なされる場合もあります。従って、継続性のある浮気を立証するために、最低でも2〜3回の証拠が必要となります。また、継続性があると判断されれば、浮気によって受けた精神的苦痛が成立し慰謝料に影響する場合もあります。
3.間接証拠の例
・継続して綴った日記。
・本人が浮気を認めた書面や録音テープ。
・浮気相手との手紙やメール。
・ホテル、飲食店、タクシーなどの領収書。
・クレジットカードの明細書。
・第三者の証言。
※勿論間接証拠のみでは不貞を立証するのに不十分ですが、間接証拠を数多く提出することができれば常識的な推定力が働き、より裁判や慰謝料請求を有利に進めることが期待できます。
■留意点
1.不貞の証拠を完全に掴むまでは、決して相手に問いただしたりはしないことです。なぜなら、警戒されて証拠を押さえる機会を失ってしまう可能性があるからです。
2.同様に、証拠が確保されるまでは別居状態にしないことです。これは婚姻破綻後の行為であると相手が主張したり、裁判官が見なしたりすることを防ぐためです。
3.「婚姻を継続し難い重大な事由」として「相手の暴力」を主張されないため、たとえ夫婦喧嘩をしても絶対に暴力を振るわないようにしましょう。
4.浮気相手からの慰謝料請求を視野に入れているのであれば、浮気相手を訴えるために氏名や住所などを明らかにしておかなければなりません。
5.相手が一方的に資産を売却したり、貯金を引き出したりするなどの事態を防止するため、印鑑や重要書類の確保に努めましょう。
《離婚時のおける決定事項》
離婚の際には夫婦間で取り決める事項がいくつかあり、「慰謝料」「養育費」「財産分与」「親権・監護権」などが挙げられます。
「慰謝料」
慰謝料とは不貞行為や暴力などにより精神的、肉体的な苦痛を与えた有責者に対する損害賠償請求です。慰謝料は有責配偶者だけではなく、有責行為に加担した人物(浮気相手など)へも請求が可能となりますので、請求するのであればその人物の氏名や住所を明確にする必要があります。また、慰謝料請求を行う場合は有責行為に関する証拠を揃えなければなりません。慰謝料の金額については有責の度合い、婚姻期間、相互の経済力、子供の有無、財産分与の金額などによって決定しますから一概にはいえませんが、300〜500万円程度が相場のようです。なお、離婚成立後でも3年以内であれば請求することはできますが、相手方は簡単に応じないのが現状です。
「養育費」
養育費とは子供を育てるのに必要な費用ですから、子供が自立するまでは親としての義務を果たすため、養育費を分担しなければなりません。父親と母親の経済状況により負担する割合は異なりますし、子供の人数によっても変わってきますが、子供を監護する側への支払いは月額2〜6万円程度が相場のようです。
「財産分与」
財産分与とは婚姻中に協力して夫婦で築き上げた財産について分配することをいいます。勿論財産だけではなく負債に関しても同様の扱いとなります。分配の対象となる財産は預貯金や生命保険、土地・建物といった不動産や住宅ローン、有価証券、家具や美術品、自動車、受給間近の退職金や年金などが挙げられます。一般的に夫婦共働きの場合は均等に分与され、片方が専業主婦(主夫)の場合は3分の1程度の分与となります。なお、離婚成立後でも2年以内であれば請求することができます。
「親権・監護権」
親権とは未成年の子供に対する「身上監護権」と「財産管理権」をいいます。身上監護権は子供を養育・教育する権利で、財産管理権は子供の財産の管理を行う権利です。このうち「身上監護権」のみ与えられるのが監護権ということになります。一般的には親権者が監護権も持つ場合が多いようです。